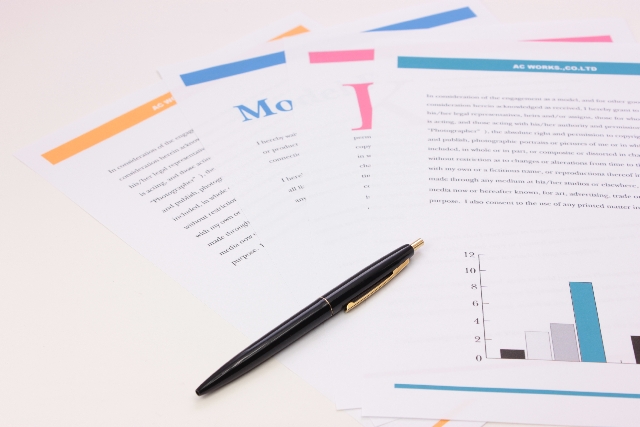


先月会社を自己都合で退職しました。明日失業保険を申請しに行きます。そこでよく解らない事があるんですが…失業保険申請中は旦那の扶養に入れないんですか?
というより旦那の社会保険には入れないんですよね?そこは調べて昨日国保と国民年金の申請をしました。転職は希望に沿えば正社員で働きたいのですが、なければパートで働きたいと思っています。もしパートで働く事になれば失業保険が切れた時に旦那の扶養に入ればいいですか?失業保険、扶養、国保、社会保険のシステムがよく解らなくて、私の様な場合どうするのが1番いいのか教えて下さい。宜しくお願いします。
というより旦那の社会保険には入れないんですよね?そこは調べて昨日国保と国民年金の申請をしました。転職は希望に沿えば正社員で働きたいのですが、なければパートで働きたいと思っています。もしパートで働く事になれば失業保険が切れた時に旦那の扶養に入ればいいですか?失業保険、扶養、国保、社会保険のシステムがよく解らなくて、私の様な場合どうするのが1番いいのか教えて下さい。宜しくお願いします。
失業保険申請中は大丈夫なはずですが?
(しかも失業保険は一か月108,000円以上ありますか?)
おそらく失業保険の受給までけっこう時間がかかりますよね。
1か月以上かかるようであれば、
失業保険は待機中という旨を扶養申出書に書いて、
離職票のコピーを提出し、退職した旨を伝え、
旦那様加入の保険組合に被扶養者異動届を提出されてはどうでしょうか?
収入の欄は130万円未満の金額を書きましょう。
正社員で入社されたらそちらになるので、
どっちみち一緒ですよ。
(しかも失業保険は一か月108,000円以上ありますか?)
おそらく失業保険の受給までけっこう時間がかかりますよね。
1か月以上かかるようであれば、
失業保険は待機中という旨を扶養申出書に書いて、
離職票のコピーを提出し、退職した旨を伝え、
旦那様加入の保険組合に被扶養者異動届を提出されてはどうでしょうか?
収入の欄は130万円未満の金額を書きましょう。
正社員で入社されたらそちらになるので、
どっちみち一緒ですよ。
失業保険をもらい始めたのですが、日額3600円くらい以上なら、主人の扶養からはずれないといけないとか前に会社から言われた気もするのですが、
私は日額4600円ちょいで90日間支給です。失業保険は収入とは関係ないのに扶養から外れなきゃならないんですか??国保に入れば、保険料や年金を払わなきゃいけないし、扶養のままでいたら後々何か徴収されたりするんですか??
私は日額4600円ちょいで90日間支給です。失業保険は収入とは関係ないのに扶養から外れなきゃならないんですか??国保に入れば、保険料や年金を払わなきゃいけないし、扶養のままでいたら後々何か徴収されたりするんですか??
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
ちなみに通勤費も収入として計算してください。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
逆に、失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
失業給付は働く意思があるとみなされ、
生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされるので
基本的に扶養に入れません。
雇用保険の傷病手当金や、出産手当金も
失業手当の代用としてこの収入に含みます。
日額制限は全く同じです。
最終回の実際の支給があった月の翌月から扶養に入れます。
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
ちなみに通勤費も収入として計算してください。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
逆に、失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
失業給付は働く意思があるとみなされ、
生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされるので
基本的に扶養に入れません。
雇用保険の傷病手当金や、出産手当金も
失業手当の代用としてこの収入に含みます。
日額制限は全く同じです。
最終回の実際の支給があった月の翌月から扶養に入れます。
共働きですが失業しました。扶養していた子供達は会社員である妻の健康保険で扶養にしてもらい、私は失業保険申請し自治体の国民健康保険という選択でいいでしょうか?
選択肢としては、①奥様の健康保険にお子様のと一緒に被扶養者として入れてもらうこと。これには、条件があり、
今の収入だけならば、失業保険をどのくらいもらえるかによります。健康保険の被扶養者になるには年間収入が
130万未満であること。
つまり失業給付が130万÷12より下回るかによります。下回るのであれば、扶養に入れてもらえるほうが、
保険料がゼロなのでお得です。ただ、旦那さまのプライドとか、奥様が会社に言いづらいとかいろんな問題がありますが、
そういう選択肢もあります。
②あとは、あなたのおっしゃるように国民健康保険の加入となりますが、保険料減額制度は
退職の理由によって使えるのでこれは、一度自治体に確認を。
③もうひとつ、あなたが加入していた健康保険の任意継続被保険者になるという制度も健康保険にはありますが、
これは、あなたが会社の辞めたときの給料の額(28万くらい)によって使うことも便利な場合もあります。これには、
辞めた日の翌日から20日内に申請をとなっています。
色々お話させていただいたのですが、まず、①で失業給付がどのくらいもらえるのかでお子様と一緒に扶養に入ることを
検討され、そのあと辞める時にお給料と現在辞めてどのくらいたっているかで②か③を検討するのが、社会保険の考え方です。
奥様とお話したうえでご検討ください。
今の収入だけならば、失業保険をどのくらいもらえるかによります。健康保険の被扶養者になるには年間収入が
130万未満であること。
つまり失業給付が130万÷12より下回るかによります。下回るのであれば、扶養に入れてもらえるほうが、
保険料がゼロなのでお得です。ただ、旦那さまのプライドとか、奥様が会社に言いづらいとかいろんな問題がありますが、
そういう選択肢もあります。
②あとは、あなたのおっしゃるように国民健康保険の加入となりますが、保険料減額制度は
退職の理由によって使えるのでこれは、一度自治体に確認を。
③もうひとつ、あなたが加入していた健康保険の任意継続被保険者になるという制度も健康保険にはありますが、
これは、あなたが会社の辞めたときの給料の額(28万くらい)によって使うことも便利な場合もあります。これには、
辞めた日の翌日から20日内に申請をとなっています。
色々お話させていただいたのですが、まず、①で失業給付がどのくらいもらえるのかでお子様と一緒に扶養に入ることを
検討され、そのあと辞める時にお給料と現在辞めてどのくらいたっているかで②か③を検討するのが、社会保険の考え方です。
奥様とお話したうえでご検討ください。
退職後、失業給付終了後の税金、年金、健康保険について
5月に退職し、1月~5月分の給与+決算賞与=102万程でした。
現在職業訓練校を受講しています。
失業保険を受給し、国民年金、国民健康保険、納税通知の税金を納めてきました。
10月の4週目で職業訓練校も終わり、同時に失業給付が終了するので、主人の扶養に入ろうと考えているのですが、市民税、県民税はいつまで自分で収め、いつから扶養に入るのでしょうか。
また、こういった場合の年金、健康保険は11月から扶養に入るものでしょうか。
10月の終了した時点で切り替えしてもらうものでしょうか。
11月、12月バイトやパートを行い収入を得たとしても月額130万以下なら払うものとしてはかわりがないのでしょうか。
5月に退職し、1月~5月分の給与+決算賞与=102万程でした。
現在職業訓練校を受講しています。
失業保険を受給し、国民年金、国民健康保険、納税通知の税金を納めてきました。
10月の4週目で職業訓練校も終わり、同時に失業給付が終了するので、主人の扶養に入ろうと考えているのですが、市民税、県民税はいつまで自分で収め、いつから扶養に入るのでしょうか。
また、こういった場合の年金、健康保険は11月から扶養に入るものでしょうか。
10月の終了した時点で切り替えしてもらうものでしょうか。
11月、12月バイトやパートを行い収入を得たとしても月額130万以下なら払うものとしてはかわりがないのでしょうか。
>市民税、県民税はいつまで自分で収め、いつから扶養に入るのでしょうか。
「住民税(市県民税)」は、前年(平成18年1/1~12/31)の所得に対しては、本年の6月から翌年5月まで納付することになります。同様に本年分の所得に対しては、翌年の6月から翌々年5月までとなります。
>また、こういった場合の年金、健康保険は11月から扶養に入るものでしょうか。
健康保険の扶養は「被扶養者」といいますが、被扶養者となる時点で「その後」の1年間の収入が130万円未満(月額換算108,333円以下)であれば被扶養者となり得ます。
「住民税(市県民税)」は、前年(平成18年1/1~12/31)の所得に対しては、本年の6月から翌年5月まで納付することになります。同様に本年分の所得に対しては、翌年の6月から翌々年5月までとなります。
>また、こういった場合の年金、健康保険は11月から扶養に入るものでしょうか。
健康保険の扶養は「被扶養者」といいますが、被扶養者となる時点で「その後」の1年間の収入が130万円未満(月額換算108,333円以下)であれば被扶養者となり得ます。
関連する情報